2026年度の税制改正に向けて、金融庁が新たに構想している「プラチナNISA」。これは、65歳以上の高齢者を対象とした非課税投資制度であり、従来のNISA制度では除外されていた「毎月分配型の投資信託」を対象に含めることが大きな特徴です。
プラチナNISAとは?概要と注目ポイント
対象者:
65歳以上の高齢者が対象。
投資対象:
毎月分配型の投資信託が新たに非課税枠の対象に。
制度の特徴:
- 現行NISAとは別枠で運用される見込み
- 現行NISA口座からの1回限りのスイッチング(毎月分配型への移行)も可能に
- 非課税投資枠の上限額は未定だが、現行の生涯投資枠(1,800万円)とは別設定が有力視
メリット:高齢者の生活を支える新しい選択肢
1. 定期的な現金収入を確保
毎月分配型投信は、年金に加えて毎月の分配金を得られるため、生活資金の安定に貢献します。
2. 非課税による手取りアップ
分配金が非課税となることで、実質的な可処分所得が増え、生活の質の向上が見込まれます。
3. 眠っていた資金の活用
家庭内に眠る預貯金を資産運用に回すことで、経済活性化と個人資産の有効活用が進みます。
デメリットと注意点:リスクを理解して活用を
1. 元本取り崩しリスク
毎月分配型は運用実績に関わらず分配金が支払われるため、元本を切り崩す「タコ足分配」となる可能性があります。
2. 手数料が高い傾向
毎月分配型投信は販売手数料や信託報酬が高めで、長期投資には不利となるケースも。
3. 金融リテラシーが求められる
分配の仕組みやリスクを理解しないまま購入すると、資産が予想以上に減少する恐れもあります。
なぜ今、毎月分配型が注目されているのか?
かつて「グロソブ(グローバル・ソブリン・オープン)」の名で知られた毎月分配型投信は、2000年代前半に高齢者を中心に一大ブームとなりました。安定的な収入を求めるニーズに応える形で普及しましたが、リーマン・ショック後にはタコ足分配による元本減少が問題となり、信頼を失いました。
それでも現在、高齢者の生活費補填ニーズに応える手段として見直されており、プラチナNISAの導入はその流れを後押しするものです。
四半期分配型投信という選択肢
毎月ではなく、四半期ごとに分配される投信は、過剰な資産取り崩しを防ぎ、運用効率を維持しやすいのが特徴です。
メリット:
- より安定した分配原資の確保
- ファンドの収益状況に合わせた分配が可能
- 長期運用に適した設計
代表的なファンド:
- 楽天・高配当株式・米国ファンド(SCHD連動)
- SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(VYM連動)
米国ETFの選択肢:
- VOO(S&P500連動)
- IVV(iシェアーズ・S&P500)
これらはすべて四半期分配でありながら、安定した配当実績と低い経費率で人気があります。
プラチナNISAの将来展望
制度は2026年度の税制改正に盛り込まれる方向で検討が進められており、具体的な導入時期・制度内容は今後の政府発表を待つ必要があります。
まとめ:プラチナNISAを活かすには「理解」がカギ
高齢者の資産活用を支援する制度として期待されるプラチナNISA。しかし、毎月分配型投信のリスクや特性を理解せずに利用することは、資産の目減りにつながる可能性があります。
重要なのは「分配金=利益」ではなく、「自分の資産を計画的に取り崩す手段」としての認識。制度の活用にあたっては、商品性やリスクを理解し、自身のライフプランに応じた選択を行うことが不可欠です。ただし信託報酬には注意が必要ですね。(出来るだけ低コスト)
今後、プラチナNISAの正式な制度化に向けて、情報収集と準備を進めていくことが、安心で豊かなセカンドライフの第一歩となるでしょう。




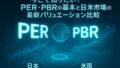
コメント