どっちが優れている?世界株vs米国株の“リスクとリターン”を徹底分析
― 投資初心者から上級者まで一生使える判断基準 ―
- ■ はじめに:なぜ今「オルカン vs S&P500」が注目されるのか
- ✅ 第1章 まずは構造の違いを理解する:両者は“前提”が違う
- ✅ 第2章 【リターン比較】20年で見るとS&P500が圧倒
- ✅ 第3章 【リスク分析①】標準偏差(値動きのブレ幅)を比較
- ✅ 第4章 【リスク分析②】最大ドローダウン(暴落時の下げ幅)
- ✅ 第5章 【リスク分析③】シャープレシオ(効率性)
- ✅ 第6章 【リスク分析④】地域リスクの違い
- ✅ 第7章 【リスク分析⑤】セクター依存度の差
- ✅ 第8章 【総合比較表】
- ✅ 第9章:NISAではどちらが最適か?
- ✅ 第10章:じゃあS&P500は不要なのか?
- ✅ 第11章:最適な解答は「オルカン+S&P500」の組み合わせ
- ✅ 第12章:投資初心者・中級者・上級者ごとの最適解
- ✅ 第13章:まとめ(この記事の結論)
- ✅ おわりに
■ はじめに:なぜ今「オルカン vs S&P500」が注目されるのか
先日、株価指数算出大手の米MSCIは、代表的な全世界株指数「MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(ACWI)」に日本株のキオクシア、JX金属、荏原、西武ホールディングス、日本株の組み入れ数が純増になるのは3年9カ月ぶりとなります。
近年、つみたてNISA・新NISAの普及によって、
世界株インデックス(オールカントリー=オルカン)と
米国株インデックス(S&P500) の比較が、投資家の関心事になっています。
「どっちが儲かる?」
「暴落に強いのはどっち?」
「NISAで買うならどちらが正解?」
結論から言えば、
- 最大リターン:S&P500
- 暴落耐性・安定性:オルカン(MSCI ACWI)
- 総合最適化:オルカン中心+S&P500の組み合わせ
という形になります。
この記事では、
✅ 標準偏差(リスク)
✅ 最大ドローダウン(暴落時下落幅)
✅ シャープレシオ(効率性)
✅ 地域リスク・通貨リスク
✅ セクター偏重の影響
✅ NISAとの相性
といった本格的な分析を使いながら、
「あなたに最適なのはどっちなのか」を判断できるよう徹底解説していきます。
✅ 第1章 まずは構造の違いを理解する:両者は“前提”が違う
オルカンとS&P500は、そもそもの投資対象が大きく異なります。
▼ オルカン(MSCI ACWI)
世界49カ国、約3,000銘柄に投資できる“全世界インデックス”。
- 米国:62~64%
- 日本:5~6%
- 英国:3~4%
- 欧州:合計15%前後
- 新興国:10~11%
世界の平均点を取る“広域分散型”の指標です。
▼ S&P500
米国の主要500社で構成される“米国株の代表指数”。
- 国は米国のみ
- 通貨はドルのみ
- ハイテク比率は約35~40%
米国の成長力を100%取りに行く“集中型”の指標です。
✅ 両者の本質は、
オルカン=世界経済平均点
S&P500=米国一点突破
という構造的な違いにあります。
✅ 第2章 【リターン比較】20年で見るとS&P500が圧倒
2003〜2023年の長期データでは、
- S&P500:年率10〜12%
- オルカン:年率6〜7%
ここは誰が見ても明確にS&P500が上回ります。
理由は明白で、
- GAFA+NVIDIA+半導体
- 米国経済のイノベーション力
- 株主還元(自社株買い)の文化
- 資本市場の規模
これらを100%取り込むのがS&P500だからです。
✅ ただし、ここで勘違いしてはいけないこと
リターンが高い=最適とは限らない。
投資は“リスクとリターンのバランス”が本質であり、
高リターン=高リスクの裏返しです。
そこで次章からは、最も重要な“リスク”を徹底評価します。
✅ 第3章 【リスク分析①】標準偏差(値動きのブレ幅)を比較
これが投資家が見るべき最重要指標。
過去20年の標準偏差は、
- S&P500:18〜20%
- オルカン:14〜16%
標準偏差は値動きの“揺れ幅”を示します。
数字が大きいほどブレが大きく、下落が深くなりやすい。
つまり…
✅ オルカンはブレが小さく穏やか
✅ S&P500は激しく動く“攻めの指数”
という構造です。
✅ 第4章 【リスク分析②】最大ドローダウン(暴落時の下げ幅)
暴落を経験したとき、投資家は“本性”が出ます。
過去の大暴落を比較すると…
| 暴落イベント | S&P500 | オルカン |
| リーマンショック | -55% | -52% |
| コロナショック | -35% | -33% |
| 2022年金利急騰 | -25% | -22% |
どの暴落でも、
✅ オルカンの方が下げ幅が小さい
という結果になります。
暴落局面では「世界分散」の本領が発揮されます。
✅ 第5章 【リスク分析③】シャープレシオ(効率性)
「リスク1単位でどれだけリターンを稼いだか」を示す指標。
直近10年では、
- S&P500:0.7〜0.8
- オルカン:0.6前後
→ 投資効率はS&P500が高い
ただし、これは「好調な米国相場」が続いたから得られた結果でもあり、
永続的に続くわけではありません。
✅ 第6章 【リスク分析④】地域リスクの違い
▼ S&P500
- 米国1国集中
- 米ドル1通貨
- FRBの政策による影響が100%直撃
→ 米国が悪くなると一発で下落
例:
2022年の急激な利上げ → S&P500は大きく下落した典型例。
▼ オルカン
- 米国62%
- 日本・欧州・新興国が38%
- 通貨も複数(ドル、ユーロ、円、人民元ほか)
→ 米国が悪くても他国がクッションになる
通貨の分散も大きく、
為替リスクも相対的に軽減されます。
✅ 第7章 【リスク分析⑤】セクター依存度の差
▼ S&P500
IT比率:35〜40%
AI・半導体・ハイテクに強く依存。
→ Tech下落=指数全体が下落
▼ オルカン
- IT:約25%
- そのほかは金融、ヘルスケア、資本財、公益など広く分散
→ 特定セクターリスクが薄い
✅ 第8章 【総合比較表】
| 項目 | オルカン | S&P500 |
| 分散 | ★★★★★ | ★★ |
| 米国依存 | 中 | 超高い |
| リターン | ★★★ | ★★★★★ |
| リスク | ★★★ | ★★★★★ |
| 暴落耐性 | ★★★★ | ★★ |
| 通貨分散 | ★★★★★ | ★★ |
| セクター分散 | ★★★★ | ★★ |
| NISA適正 | ◎ | ○ |
✅ 第9章:NISAではどちらが最適か?
新NISAは“非課税×長期運用”が前提──
つまり 暴落に強い資産 が本質的に向いています。
✅ 結論:
NISAのコアはオルカン(全世界株)が最適解。
理由は明確で、
- 大暴落でも下落がS&P500より浅い
- 世界平均に追随するだけで良い
- 自動リバランスで放置できる
- 通貨リスクが分散される
- 新興国の成長も取り込む
投資効率を最大化するには、
“世界全体の成長”に丸ごと賭けるのが合理的だからです。
✅ 第10章:じゃあS&P500は不要なのか?
結論:不要ではありません。むしろ必要です。
S&P500には、
- 米国の圧倒的な成長力
- GAFA+NVDAの超成長
- 株主還元文化(自社株買い)
- 世界最強の資本市場
という、“世界で最も強い株式市場”のメリットがあります。
そのため、
✅ 追加リターンが欲しい人
✅ オルカンだけでは物足りない人
✅ 米国株比率を上げたい人
にはS&P500が欠かせません。
✅ 第11章:最適な解答は「オルカン+S&P500」の組み合わせ
プロ投資家が採用する王道戦略が
コア・サテライト戦略(Core & Satellite)。
▼ コア(核心):オルカン 70~80%
- 世界平均の安定した成長
- 暴落時に強い
- 長期でリスクを吸収できる
▼ サテライト(追加):S&P500 20~30%
- 米国の超成長を取り込む
- リターンの最大化に寄与
- ハイテクの爆発力をキャッチ
✅ この組み合わせが「最も効率的」
・リスクを抑えつつ
・リターンを取りに行ける
最適化されたポートフォリオになります。
✅ 第12章:投資初心者・中級者・上級者ごとの最適解
✅ 初心者
迷わずオルカン100%
→ 世界の成長を平均的に取り込めるのが最強
✅ 中級者
オルカン80%+S&P500 20%
→ 米国の成長も狙いたい人に最適
✅ 上級者
オルカン70%+S&P500 20%+NASDAQ系10%
→ ハイテクの爆発的成長を最適リスクで取り込みたい方向け
✅ 第13章:まとめ(この記事の結論)
■ リターン最大:S&P500
■ リスク最小:オルカン
■ 暴落に強い:オルカン
■ 攻撃力が高い:S&P500
■ NISA向け:オルカン
■ 最適なのは「組み合わせ」
✅ おわりに
投資において最も重要なのは、
「マーケットに残り続けること」。
そのためには、
暴落に強く、長期で安定するオルカンを“核”にすることが合理的です。
ただし、
“米国の超成長”を取りに行くならS&P500は欠かせません。
そしてプロの行動は常に
✅ オルカン(世界分散)をベースに
✅ S&P500(成長)を追加する
という構造になっています。
この戦略は
初心者〜上級者まで効果があり、
長期運用における最適解とかんがえています。






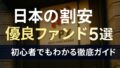
コメント