はじめに:なぜ今「高配当株指数」が注目されるのか?
2025年現在、日本の株式市場では高配当株投資が個人投資家・機関投資家の双方から注目を集めています。
その背景には以下のような理由があります。
- 金利上昇局面で債券利回りは改善しているものの、株式配当利回りの魅力も依然として高い
- インフレ環境下で配当金の実質価値を確保する重要性が増している
- 日経平均株価の高値圏推移で値上がり益だけに頼らない運用が求められている
- 長期投資志向の高まりによる安定収入源としての配当への関心
この中で、特に注目されているのが日本経済新聞社が算出する「日経平均高配当株50指数」と「日経累進高配当株指数」です。
どちらも「高配当株」という共通テーマを持ちながら、選定基準や投資戦略の方向性が異なります。
本記事では、この2つの指数を徹底比較し、それぞれの特徴・構成銘柄・投資方法・活用戦略をわかりやすく解説します。
第1章 日経平均高配当株50指数とは?
1-1. 概要
- 英語名: Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index
- 算出開始: 2017年1月10日
- 構成銘柄数: 50銘柄
- 母集団: 日経平均株価(225銘柄)
- 選定基準:
- 日経平均採用銘柄の中から、予想配当利回り上位75銘柄を抽出
- その中から流動性(売買代金)上位50銘柄を選定
- 日経平均採用銘柄の中から、予想配当利回り上位75銘柄を抽出
- リバランス頻度: 年2回(1月と7月)
1-2. 特徴
- 配当利回りの高さを最優先
- 銘柄入れ替えが比較的多く、トレンドに合わせた構成変化
- 高配当ETF(例:NEXT FUNDS 日経平均高配当株50 ETF【1489】)のベンチマークとして利用される
1-3. メリットとデメリット
メリット
- 高利回り銘柄に集中投資できる
- 流動性が高い銘柄が多く、売買しやすい
- ETFや投資信託で簡単に分散投資可能
デメリット
- 増配や配当維持の実績は必須ではないため、将来減配のリスクあり
- 銘柄入れ替えが多く、長期保有前提では予想外の売買が発生する可能性
1-4. 2025年8月時点の代表銘柄例
- INPEX(1605)
- 日本たばこ産業(2914)
- 川崎汽船(9107)
- 武田薬品工業(4502)
- 東ソー(4042)
- 日本郵船(9101)
- ブリヂストン(5108)
- AGC(5201)
- 日本製鉄(5401)
- 三井化学(4183)
第2章 日経累進高配当株指数とは?
2-1. 概要
- 英語名: Nikkei Progressive High Dividend Index
- 算出開始: 2021年2月15日
- 構成銘柄数: 30銘柄
- 母集団: 東証プライム市場上場銘柄
- 選定基準:
- 10年以上連続で増配または配当維持している企業
- 予想配当利回りが高い順に30銘柄を選定
- 10年以上連続で増配または配当維持している企業
- リバランス頻度: 年1回(6月末)
2-2. 特徴
- 「累進配当方針」を重視
- 増配・配当維持実績のある企業のみを採用するため、配当の安定性が高い
- 長期保有向きの銘柄構成
2-3. メリットとデメリット
メリット
- 減配リスクが低く、安定収入が期待できる
- 長期投資に向いた銘柄構成
- 配当+株価成長の両面でリターンを狙える
デメリット
- 高配当利回りでも増配実績がない企業は除外されるため、利回りだけで見ると劣る場合あり
- 銘柄数が少なく、業種分散が限定的になる可能性
2-4. 2025年8月時点の代表銘柄例
- 武田薬品工業(4502)
- 東ソー(4042)
- 日本化薬(4272)
- 三菱HCキャピタル(8593)
- アステラス製薬(4503)
- 上組(9364)
- 王子ホールディングス(3861)
- 三井住友トラストHD(8309)
- 積水ハウス(1928)
- SBIホールディングス(8473)
第3章 両指数の共通銘柄と違い
3-1. 両方に採用されている銘柄(2025年8月時点)
- 武田薬品工業(4502)
- 東ソー(4042)
3-2. 選定基準の違い
| 項目 | 日経平均高配当株50指数 | 日経累進高配当株指数 |
| 母集団 | 日経平均構成225銘柄 | 東証プライム全銘柄 |
| 銘柄数 | 50銘柄 | 30銘柄 |
| 選定基準 | 高配当利回り上位+流動性 | 10年以上連続増配または配当維持+高配当利回り |
| リバランス | 年2回 | 年1回 |
| 投資スタイル | 短中期向け | 長期安定志向向け |
第4章 投資戦略と活用方法
- インカムゲイン重視派
→ 累進高配当株指数型ファンドをコアに据え、安定収入を狙う - 配当+値上がり益狙い派
→ 高配当株50指数型ETFを活用し、市場動向に合わせた売買 - 両方組み合わせ派
→ 株価調整局面で高配当株50型を仕込み、累進型を長期保有で配当再投資
第5章 まとめ
- 高配当株50指数は「利回り重視で流動性高め」、累進高配当株指数は「配当の安定性と持続性重視」
- 両方に共通する銘柄は少なく(2025年8月時点で武田薬品工業と東ソー)、選定思想が異なる
- 投資目的に応じて使い分け、あるいは併用が有効
第6章 ETF・投資信託の具体的な銘柄例とバックテスト比較
6-1. 「日経平均高配当株50指数」をベンチマークとする代表ETF・投資信託
日本市場において、最も代表的なのが以下のETFです。
- NEXT FUNDS 日経225高配当株50 ETF(コード:1489)
このETFは「日経平均高配当株50指数(配当込み【Total Return】)」の動きを追うよう設計されています。4回/年(1月・4月・7月・10月)に分配が行われ、信託報酬は年率約0.308%(税込)です。
(参考データ)
YTDリターン:約7.5%、1年間のリターン:20.3%程度です。
- 399A 上場インデックスファンド(日経平均高配当株50)(信託報酬:約0.15%)
こちらは三菱UFJ国際投信による ETF で、同じ指数を対象としています。
6-2. 『日経累進高配当株指数』を対象とするファンドは?
現時点では、累進高配当株指数を対象とした専用ETFや投信は確認できておりません。
ただし、今後の拡張が見込まれるテーマであり、増配企業への関心が高まる中、注目しておく価値があります。
6-3. バックテスト比較:高配当指数 vs 日経平均(TR)
「日経平均高配当株50指数(トータルリターン)」と、日経平均株価(トータルリターン)の比較です(年次リターン)。
| 年 | 高配当50指数(TR) | 日経225(TR) |
| 2020年 | –9.70 % | +18.26 % |
| 2021年 | +28.24 % | +6.66 % |
| 2022年 | +24.60 % | –7.34 % |
| 2023年 | +40.55 % | +30.96 % |
| 2024年 | +25.17 % | +21.33 % |
| 年初来 | +4.43 % | +4.06 % |
分析ポイント:
- リスク(年間標準偏差):
高配当50指数:1年→10.35%、3年→12.73%、5年→13.55%
日経225:1年→13.19%、3年→14.96%、5年→15.31%。 - 高配当50指数はリスクが低めで、かつリターンも比較的優位という傾向があります。
- また、基本指標として 配当利回り や PER/PBR も確認できます。
高配当50指数:配当利回り 4.29%、PER 12.30、PBR 0.82、ROE 6.71%
日経225:配当利回り 1.95%、PER 20.47、PBR 2.00、ROE 9.77%。
→ 高配当50指数のほうが「抑えられた株価水準」であり、割安かつ収益性指標が魅力的という傾向ですね。
6-4. Tracers インデックスファンドの概要
Tracers 日経平均高配当株50インデックスの特徴と活用法
- 正式名称:「Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型)」(投資信託)
- 運用開始日:2024年1月31日
- 委託会社:日興アセットマネジメント
- ベンチマーク:「日経平均高配当株50指数(トータルリターン)」
- 決算頻度:年6回(奇数月の30日)
- 信託報酬(管理費用含む):年率 0.10725%(とても低コスト)
- 購入手数料:無料(ノーロード)
6-5. パフォーマンスと評価
- 基準価額(2025年8月8日時点):11,597円(前日比 +1.41%)
- トータルリターン(設定来):年率+12.15%、累計+18.24%
- 1年リターン:+3.26%
- リスク(標準偏差、1年):約10.24
- 分配金:直近は100円/回。設定初期は無分配の回もありましたが、現在は奇数月ごとに支払われています
- 純資産残高:約224億円(2025年8月時点)
** 評判・比較ポイント**
- ETF「1489」とほぼ同内容ですが、信託報酬が低い点で人気があります。
- 主な組入上位業種としては「銀行業」「海運業」「卸売業」「保険業」「鉄鋼」などが多く含まれ、業種分散もされている構成です。
- 評価面では、「低コスト」「年6回の分配で現金収入が得やすい」という点が好印象ですが、長期の複利効果を重視するなら分配金が資産形成には向かないという意見もあります。
第7章 両指数+Tracersファンドの総括比較(表形式)
| 指標・ファンド名 | 特徴 | メリット | デメリット |
| 日経平均高配当株50指数 | 高配当利回り+流動性重視 | 高利回り、流動性が高い | 増配実績保証なし、銘柄入替頻度高い |
| 日経累進高配当株指数 | 増配・配当維持10年以上 | 配当の安定性・長期投資向き | 利回りは低め、構成銘柄少ない |
| Tracers インデックス | 高配当指数連動・年6回の分配 | 低コスト、定期分配で現金収入あり | 複利運用には向かない、分配依存リスク |
第8章 投資設計への具体的応用提案
- 安心のインカム設計
→「日経累進高配当株指数」の銘柄をコアに据え、確実な配当収益を目指す。 - 市場連動+収益効率型
→「日経平均高配当株50指数」や「Tracers インデックス」で市場の高配当トレンドも取り入れる。 - 分散×戦略的併用
→例:資産比率で累進型を50%、高配当50型ETFまたはTracersを30%、残りを他の資産へ。 - 投資目的別の使い分け
- 定期、安定した収益が欲しい人→「Tracers」、分配金型で収入を得る設計も有効
- 非課税枠(成長投資枠等)活用したい人→組み合わせによっては効率的な資産形成が可能
- 定期、安定した収益が欲しい人→「Tracers」、分配金型で収入を得る設計も有効
最終まとめ
- 日経平均高配当株50指数は「高利回り+売買流動性重視」で、ETF(1489など)に投資しやすく、リスクを抑えながら収益も狙えます。
- 日経累進高配当株指数は「10年以上の増配・配当維持実績」を条件にした、長期志向型のインカム投資向き。今後のETF化に要注目です。
- 両者を目的別・期間別に組み合わせて投資設計すれば、より強固で効率的なインカムポートフォリオが構築可能です。
日本株指数は軒並み高値更新し絶好調の兆しと見られますが、今回の決算は下方修正も多くなぜ爆上げしているかを考えてみましょう。一つは積み重なってきた信用売り(約1兆円程度)を買い戻さざるを得なくなった末の値上がりかと考えていますがいかがでしょうか。読者のみなさんもこれからおきるであろう暴落も意識しつつ慎重な姿勢で運用をしていきましょう!暴落時は買い時ですからね。😊

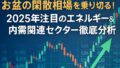

コメント