2025年3月28日に発表された米国の経済指標により、スタグフレーションへの懸念が高まりました。主な指標は以下のとおりです。
1. 個人消費支出(PCE)価格指数:
- 2月のコアPCE価格指数(食品とエネルギーを除く):前年同月比で2.8%上昇し、前月の2.6%から加速しました。
2. ミシガン大学消費者信頼感指数(3月確報値):
- 消費者信頼感指数:57.0と、前月の64.7から低下し、2年ぶりの低水準となりました。
これらの指標は、物価上昇と消費者信頼感の低下を示し、スタグフレーションへの懸念を強める要因となっています。
この指標を受け米国の主要株価指数は以下の通り下落しました:
- S&P 500:前日比 -112.37ポイント(-1.97%)の5,580.94で取引を終了しました。
- ダウ工業株30種平均:前日比 -715.80ポイント(-1.69%)の41,583.90で終了しました。
- ナスダック総合指数:前日比 -481.04ポイント(-2.70%)の17,322.99で取引を終えました。
さらに週明け(年度末)前場の日本株式市場の日経平均は一時-1500円大幅下落に陥っています。(終値で-1502.77円)
スタグフレーションとは
「スタグフレーション(Stagflation)」とは、以下の2つの経済現象が同時に起こる状態を指します:
✅ 1. 経済の停滞(Stagnation)
景気が悪く、GDPの成長が鈍化、あるいはマイナス成長している状態。
✅ 2. インフレーション(Inflation)
物価が上昇し、生活費が上がっている状態。
🔁 通常の経済理論との矛盾
一般的には、景気が悪ければ物価は下がりやすい(デフレ)とされますが、スタグフレーションは「景気が悪いのに物価が上がる」という異常事態です。
🧠 原因の例
- 原材料(特に石油など)の価格高騰
- 外的ショック(戦争・パンデミックなど)
- 金融政策のミス(過剰な金融緩和など)
🧩 日本や世界での事例
- 1970年代のオイルショック後のアメリカや日本
- 現代でも、エネルギー価格の高騰やサプライチェーンの混乱によって「スタグフレーション懸念」がたびたびニュースになります。
⚠️ スタグフレーションのリスク
- 企業の利益が減り、雇用が悪化
- 家計の支出が増えるのに収入は減る
- 金融政策(利下げで景気刺激 or 利上げで物価抑制)が難しい
各国の対策
そして、2025年3月現在、世界経済はスタグフレーション(景気停滞とインフレの同時進行)の懸念が高まっています。
アメリカの状況と対応策:
米連邦準備理事会(FRB)の最新の経済見通しでは、「軽度のスタグフレーション」が想定されています。これは、関税引き上げなどの政策がインフレを促進し、同時に経済成長を鈍化させる可能性があるためです。FRBは、インフレ抑制と雇用最大化という二重の責務の間で、複雑な政策運営を迫られています。
日本の状況と対応策:
日本では、2025年の春闘で平均賃上げ率が5.0%と予想されていますが、実質賃金の伸び悩みが続いています。これは、物価上昇が賃金上昇を相殺しているためです。政府と日銀は、金融緩和政策を維持しつつ、賃金と物価の好循環を目指していますが、効果は限定的とみられています。
ヨーロッパの状況と対応策:
ユーロ圏では、エネルギー価格の高騰や供給制約により、スタグフレーション的状況が長期化する懸念があります。欧州中央銀行(ECB)は、インフレ抑制のための利上げと、景気支援のための緩和策のバランスを模索しています。
中国の状況と対応策:
中国では、景気の長期低迷から脱出できない可能性が指摘されています。政府は大規模な財政出動や金融緩和を実施していますが、効果は限定的であり、構造的な問題が浮き彫りになっています。
まとめ:
各国はスタグフレーションのリスクに直面し、それぞれの状況に応じた政策対応を進めています。しかし、インフレ抑制と景気刺激の両立は難しく、今後の経済動向には引き続き注意が必要です。
日本の対策
景気減速に対して利下げをする余地はありますが、日本には利下げ余地はほぼありません。それでは、スタグフレーション(景気停滞と物価上昇の同時進行)に直面した際、日本の政策対応と国民の心構えについて考えてみましょう。
日本の政策対応:
- 金融政策の調整: 日本銀行は、長年のデフレからの脱却を目指し、2025年1月に金利を0.5%に引き上げました。 しかし、さらなる利上げは景気を冷やす可能性があり、慎重な判断が求められます。
- 財政政策の強化: 政府は、低所得者層への給付金や地方自治体への補助金など、生活費高騰への対策を含む新たな経済対策を指示しています。 これにより、消費の下支えと景気の安定化を図っています。
- 賃金と投資の促進: 継続的・安定的な賃上げと官民連携での計画的投資を通じて、需給ギャップの縮小を進めることが重要です。 これにより、賃金と物価がともに上昇する好循環を目指します。
国民の心構え:
- 資産の多様化: インフレに備え、現金だけでなく、株式や不動産、金などの現物資産への投資を検討することが有効です。 これにより、資産価値の目減りを防ぐことが期待されます。
- 外貨資産の保有: 円安による購買力低下に備え、外貨建て資産を一部保有することで、リスク分散が図れます。
- 生活防衛意識の向上: 物価上昇に対応するため、家計の見直しや節約を心がけるとともに、必要に応じて副業やスキルアップを検討することが重要です。
スタグフレーションは、政策対応が難しい経済状況ですが、政府と国民が協力し、適切な対策と心構えを持つことで、その影響を最小限に抑えることが可能です。
いろいろな要因が伴い日本株の下げ幅は大きくなっていますが、ここは冷静に考えると、分割銘柄が多く金額的にも買いやすい。株価下落で累進配当を掲げている銘柄もさらに配当率も上がっています。すなわち買い場が来ていると考えてよいのではないでしょうか?この下落相場をうまく活用し今後の資産形成の糧に!と考えていきましょう。






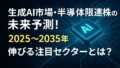
コメント