第1章|日経平均44,000円突破という歴史的局面
2025年9月、日経平均株価はついに場中で44,000円を突破しました。これは日本株投資家にとって歴史的な節目であり、バブル期を超える水準です。2024年にかけての上昇トレンドの延長線上にあるものの、やはり「ここまで来たか」と驚きを持つ投資家も少なくありません。
背景にはいくつかの要因があります。まずは円安効果です。為替が1ドル=150円台半ばで推移するなか、自動車や電機といった輸出企業の利益が押し上げられています。加えて、インバウンド需要の回復や半導体関連銘柄の好調も相場を支えています。海外投資家による資金流入も続いており、グローバルマネーが「日本株買い」に傾いていることが鮮明です。
一方で、相場水準の急上昇に対して「割高ではないか?」という懸念の声も出ています。それを測る代表的な指標が**PER(株価収益率)**です。
第2章|PER18倍超は割高か?妥当か?
現在の日経平均のPERは加重平均で約17.96倍、指数ベースでは22倍超となっています。過去を振り返ると、アベノミクス相場の平均PERは15倍前後、コロナ後の株価上昇局面でも16〜17倍程度でした。それを考えると、現状は確かに「割高圏」に入っていると判断できます。
しかし「割高=株価下落」とは限りません。米国ナスダック市場の例を見ても、PER30倍を超える状態が長く続いた時期があります。株式市場は「将来の成長期待」を先取りするため、EPS(1株利益)が後からついてくれば割高感は解消されます。つまり、今の日経平均は「期待先行型相場」と言えます。
問題は、この期待が実際の企業収益改善で裏付けられるかどうかです。もしCPIやFOMCをきっかけに米国株が失速すれば、日本株もその期待を一時的に剥がされるリスクがあります。
第3章|需給環境が良好とされる理由
それでも多くの市場参加者が「需給は良い」と口を揃えるのには理由があります。まず、信用取引の倍率です。直近の東証データでは、買い残に対する売り残の割合が低く、売り方がやや多めの状況です。これは「踏み上げ」の材料となり、株価の下支え要因になります。
さらに、海外投資家による先物買い越しが顕著です。外国人投資家は日経平均先物を大量に買い越し、ヘッジファンド勢も指数連動型の買いを積み増しています。加えて、上場企業の自社株買いや増配姿勢の強化、GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)の安定的な資金供給も需給環境を良好にしています。
つまり「高値だけど売り崩されにくい」という地合いが整っているのです。
第4章|週末のMSQ(メジャーSQ)が意味するもの
週末には**MSQ(メジャーSQ)**が控えています。これは先物やオプションの最終決済日であり、株価に大きなインパクトを与えるイベントです。過去の例を見ても、MSQ週は株価の上下が激しくなりやすい傾向があります。
例えば2020年や2022年のMSQ週では、SQ値決定後に数百円単位の乱高下が発生しました。今回も建玉が積み上がっているため、44,000円台を巡って大きな攻防になる可能性があります。特に、売り方が踏み上げられれば短期的に45,000円突破のシナリオもあり得ますし、逆に買い方がポジションを解消すれば急落リスクも否めません。
第5章|米国CPIとFOMCがもたらすインパクト 🇺🇸
最大の注目イベントは米国です。来週には**CPI(消費者物価指数)**の発表が予定されており、これはFRBの金融政策を左右する重要指標です。市場コンセンサスではインフレは緩やかに低下すると見られていますが、もし予想以上に高止まりしていた場合、利下げ期待が後退し、株式市場にマイナスとなります。
さらに**FOMC(米連邦公開市場委員会)**では、政策金利の据え置きか利下げが議論されます。声明文やドットチャート次第では、今後の金利見通しに大きな変化が出るでしょう。利下げが前倒しされると株式市場は好感しますが、逆に「インフレ根強し」と判断されれば売り圧力が強まります。
米国株が荒れると、日本株も連動して上下するため、週明けは要注意です。
第6章|日経VI(ボラティリティ・インデックス)から読み解く市場心理
現在の**日経平均VI(恐怖指数)**は24前後です。一般的に、20以下は「落ち着き」、20〜30は「やや不安」、30以上は「警戒ゾーン」とされます。つまり今は「イベント前で神経質」な状況にあると言えるでしょう。
過去を振り返ると、CPIやFOMCを控えた局面でVIが30を超えた事例もあります。今回も米国イベントが波乱要因となれば、短期的にVIが急騰する可能性は十分にあります。投資家心理はナーバスになっており、リスク管理が欠かせません。
第7章|短期シナリオ別の株価推移予測
ここで3つのシナリオを整理します。
- 強気シナリオ:CPIが予想通り、または下振れ → 利下げ期待継続 → 日経平均は45,000円突破の可能性
- 弱気シナリオ:CPIが上振れ → 利下げ期待後退 → 一時的に42,000円割れも視野
- 中立シナリオ:CPIは予想通り、FOMCも想定の範囲 → 上下に振れるがレンジ相場継続
投資家としては、このどのシナリオになっても対応できる準備が必要です。
第8章|中期トレンド:EPS改善と世界資金の行方 🌍
中期的には「日本株は上昇トレンドを維持する」という見方が有力です。円安基調と企業収益の改善、そして海外投資家の組み入れ増加が背景にあります。特に半導体関連やインバウンド消費関連は業績見通しが明るく、EPSが伸びる可能性があります。
重要なのは、今の相場が「PER主導の期待相場」から「EPS伴う実力相場」に移行できるかどうかです。もし企業業績が伴えば、44,000円台は通過点となり得ます。
第9章|投資戦略① 短期:イベント前のリスク管理
短期投資家にとっては、イベント前にポジションを軽くすることが最適解の一つです。利益確定してキャッシュ比率を上げたり、ヘッジとして日経インバースETFやVIX連動商品を活用するのも手です。特にMSQ直前は予想外の値動きが起きやすいため慎重さが求められます。
第10章|投資戦略② 中期:押し目狙いと分散投資
一方で、中期的な投資家にとっては、イベントでの調整は押し目買いのチャンスです。高配当株やインデックス投信を積み立てることで、長期トレンドの恩恵を受けられます。さらに米国株ETFや債券ETFを組み合わせることで為替リスクも分散できます。
第11章|孫子とバフェットの投資哲学から学ぶ 🧠
孫子は「勝ちて後に戦う」と説きました。つまり、有利な状況を整えてから戦うべきだということです。投資でも同じで、イベントリスクを無防備に受けるのではなく、事前に戦略を立てて臨むことが重要です。
また、ウォーレン・バフェットは「株式市場は短期的には投票機、長期的には体重計」と語りました。短期イベントで株価は乱高下しますが、最終的には企業価値に収れんしていきます。この視点を持つことが冷静な投資判断につながります。
第12章|まとめ:今取るべき姿勢
- 短期的には慎重姿勢:キャッシュ比率を高め、イベント前は守りを固める
- 中期的には強気姿勢:EPS改善と世界資金の流入に乗る
- 割高感よりもトレンドの持続性を重視
日経平均44,000円は確かに割高に見えます。しかし、需給環境や世界の資金フローを考えると、短期的な調整はあっても中期的にはさらなる高みを目指す可能性が高い局面です。投資家は「短期の波」に翻弄されすぎず、「長期の流れ」に身を置くことが重要です。本日は史上最高値をつけたあと43,459.29円で安値引けしています。利益確定売りや買い方の売り圧力が強かったようです。今週のCPI統計も気になりますが皆さんはどのような流れに身を任せますでしょうか。😅



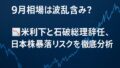

コメント