- はじめに――「株は高い?安い?」を考える最初の物差し
- 第1章|PERってなに?(まずはここだけ覚えればOK)
- 第2章|PERの「上手な見方」――数字に振り回されないコツ
- 第3章|理論株価を出す3つの王道モデル
- 第4章|期待利回り r の決め方(CAPMの考え方)
- 第5章|実務で使える「理論PER→理論株価」レシピ
はじめに――「株は高い?安い?」を考える最初の物差し
株を買うとき、最初に気になるのは「いま高いの?安いの?」ですよね。
そこでよく登場するのが PER(株価収益率) という指標です。
PERは「株価が、その会社の利益(EPS)に対して何倍まで買われているか」を教えてくれます。
💡PERが高い → 「みんなこの会社の将来に期待している」
💡PERが低い → 「利益に対して割安に見える」
ただし、数字だけで「高い=危険」「低い=チャンス」と判断するのは早計。
金利、成長性、業界特性、利益の質 などをあわせて見ないと、本当の姿を見誤ります。
本記事では、PERのやさしい基本から理論株価の出し方まで、初心者でも理解できるように丁寧に解説していきます。
第1章|PERってなに?(まずはここだけ覚えればOK)
1-1 PERの計算式
PER = 株価 ÷ 1株あたり利益(EPS)
例)株価1,800円・EPS100円 → PER=18倍
「株価は“利益の18年分”の値段がついている」とイメージするとわかりやすいです。
1-2 逆数は「益利回り」
益利回り = EPS ÷ 株価 = 1 ÷ PER
PER18倍なら、益利回りは約 5.6%(=1/18)。
つまり「この会社は、株価に対して年5.6%分の利益を生む力がある」と捉えられます。
💡銀行金利や債券利回りとざっくり比較する時に便利です。
1-3 トレーリングPERとフォワードPER
- トレーリングPER:過去1年の実績EPSで計算(“足元の現実”)
- フォワードPER:来期の予想EPSで計算(“みんなの見通し”)
景気の波や一時的な損益で見え方が変わるので、両方を並べて見るクセをつけましょう。
第2章|PERの「上手な見方」――数字に振り回されないコツ
2-1 業界ごとに“物差し”は違う
IT・AIなど成長業界はPERが高くなりがち。
電力・インフラのような成熟業界はPERが落ち着きやすい。
👉 比較は“同じ業界”の中で行うのが基本です。
2-2 金利が上がるとPERは縮みやすい
将来のお金は、金利が高いほど“いまの価値”が低く見積もられます。
- 金利↑ → 将来価値の割引がきつい → PERは下がりやすい
- 金利↓ → 将来価値が高く評価 → PERは上がりやすい
2-3 利益の「質」を見る
EPSの中身をチェックすることが大切です。
- 特別損益や為替差益で水増しされていないか
- 借金が多く無理をしていないか
- 自社株買いで“見かけ上のEPS”だけ上がっていないか
営業利益率・ROE・キャッシュフローも一緒に確認しましょう。
2-4 「PERが低い=必ずお買い得」ではない
低PERには理由があることが多いです。
構造不況、競争激化、利益低下など。
逆に高PERでも「ブランド力・参入障壁・高ROE」で正当化されることもあります。
第3章|理論株価を出す3つの王道モデル
株価が“どのくらいが妥当か”を考えるとき、「理論株価」という考え方を使います。
代表的なアプローチは次の3つです。
3-1 成長配当モデル(Gordon成長モデル)
配当が毎年一定の割合で伸びると仮定して求めます。
理論株価 P₀ = 来年配当 D₁ ÷ (期待利回り r − 成長率 g)
安定配当&緩やかな増配タイプの企業に向きます。
また、この式は 理論PER にもつながります。
理論PER(フォワード) = 配当性向 ÷ (r − g)
※成長率gは概ね g = ROE ×(1 − 配当性向) で求められます。
具体例
- ROE = 12%
- 配当性向 = 40% → 内部留保 = 60%
- 成長率 g = 12% × 0.6 = 7.2%
- 期待利回り r = 9%
→ 理論PER = 0.40 ÷ (0.09 − 0.072) = 22.2倍
→ 来期EPSが200円なら 理論株価 = 22.2 × 200 = 4,440円
📌ポイント:
r と g の差が小さいほどPERは跳ね上がる。
金利上昇(r↑)や成長鈍化(g↓)で適正PERは下がる方向です。
3-2 DCF(割引キャッシュフロー)法
将来のキャッシュフローを予測し、現在価値に割り引いて株価を出す方法。
- 各年のフリーキャッシュフローを予測
- 割引率(WACCなど)で現在価値に換算
- 企業価値 → 負債を引いて株主価値 → 株数で1株価値に換算
配当を出さない成長企業にも使えるのが特徴です。
ただし前提に敏感なので、感度分析が必須です。
3-3 残余利益モデル(Residual Income)
簿価(PBRの基)とROE−期待利回りの差で価値を積み上げるモデルです。
ROEが資本コストを上回るほど価値が増える仕組みで、
PBRとROEの橋渡しをしてくれる指標でもあります。
第4章|期待利回り r の決め方(CAPMの考え方)
r = 無リスク金利 + β × 市場リスクプレミアム
- 無リスク金利:長期国債利回りを目安
- β(ベータ):市場全体に対する株価の動きやすさ
- 市場リスクプレミアム:株式市場の追加リターン(一般的に3〜6%)
金利が上昇すれば、r も上昇し、理論PERは下がる方向になります。
第5章|実務で使える「理論PER→理論株価」レシピ
- 前提を決める
ROE・配当性向・無リスク金利・β・市場リスクプレミアム・来期EPS - 成長率 g を計算
g = ROE ×(1 − 配当性向) - 理論PER
理論PER = 配当性向 ÷(r − g) - 理論株価
理論株価 = 理論PER × 来期EPS
ミニ演習
ROE=10%、配当性向=30%、来期EPS=150円、r=8.5%
→ g = 7%
→ 理論PER = 0.30 ÷ (0.085−0.07) = 20倍
→ 理論株価 = 20 × 150 = 3,000円
第6章|感度分析で“手堅さ”を確認しよう
仮定を少し動かすだけで結果は変わります。
以下のように+/-変化を試して、リスクを見ておきましょう。
- r:±0.5%
- g:±1%
- 配当性向:±5pt
- ROE:±1%
強気・標準・弱気の3パターンを作ると、下落時の“許容ライン”が見えます。
第7章|PERの落とし穴と対策
| 落とし穴 | ありがちな誤解 | 防ぐポイント |
|---|---|---|
| 低PER信仰 | 安い=割安 | 不況・収益性低下かも。ROE・CFも確認 |
| 高PER忌避 | 高い=危険 | 高ROE・高成長企業なら合理的 |
| EPSのブレ | 一時要因で歪む | 5年平均・調整後EPSで補正 |
| 金利無視 | 金利上昇でも同物差し | 金利上昇局面ではPER縮小に注意 |
| 自社株買い効果 | EPSが“見かけ”で上昇 | CFや総還元で実力を評価 |
第8章|補助指標を“ゆるっと”セットで使う
- PBR:資産の上にどれだけ期待が乗っているか
- ROE/ROIC:資本をどれだけ効率よく使っているか
- 配当利回り・総還元性向:株主への還元姿勢
- 営業利益率・CF:実力値の確認
- PEGレシオ(PER ÷ 成長率):成長と割安のバランス
- EV/EBITDA:負債を含む企業価値で比較
👉 PERだけに頼らないことが上手な投資の第一歩です。
第9章|指数のPERを見るときのやさしい視点
「日経平均PER18倍」「S&P500 PER22倍」などニュースで見ますが、
単純比較はNGです。
- 業種構成(米はハイテク比率が高い)
- 金利・成長率の違い
- 投資家層や市場の厚み
指数PERは「大型グロースの影響が大きい」点に注意。
“中身を見るクセ”が大事です。
第10章|ケーススタディ(実例で理解)
ケースA:配当安定の成熟企業
- ROE=9%、配当性向=50% → g=4.5%
- r=8.5%、来期EPS=180円
→ 理論PER = 12.5倍
→ 理論株価 = 2,250円
成熟株は過度な高PERを正当化しにくい、という直感にも一致します。
ケースB:高ROEの成長企業(無配型)
配当モデルが使えない場合は DCF や 残余利益モデル を活用。
無配でも自社株買いがある場合は「総還元」で評価します。
第11章|初心者向けチェックリスト(保存版)
- トレーリング/フォワードPERどっちを見てる?
- 同業他社と比べた?
- ROE・配当性向からgを計算した?
- 期待利回りrは妥当?
- 理論PER→理論株価を出した?
- 感度分析は試した?
- PBR・CF・総還元も確認した?
- 一時要因を除外してる?
- 自社株買いや希薄化を考慮?
- 複数モデルで整合性を確認した?
第12章|やさしいQ&A
Q1:PERが低い株だけ買えば勝てますか?
→ いいえ。低PERには理由があります。構造不況や競争激化など。ROE・CFも確認を。
Q2:PERが高い株は危険ですか?
→ 一概にそうとは言えません。高ROE・ブランド力・参入障壁で正当化されることも。
Q3:初心者が見るべき数値は?
→ PER(実績・予想)/PBR/ROE/配当利回り/営業CF。この5つで十分です。
Q4:理論株価は“絶対”ですか?
→ いいえ。仮定に基づく目安です。だからこそ感度分析が大切です。
第13章|今日からできる“3つの練習”
- 気になる3社のPER・PBR・ROEを並べて比較
- ROE・配当性向・rから理論PERを出して理論株価を計算
- rとgを±してブレ幅を体感する
週1回この練習をするだけで、数字を見る目が格段に育ちます。
おわりに――数字の奥にある「会社の物語」を読む
PERは便利な入口の指標です。
でも最後に大切なのは、数字の奥にある“物語”。
「この会社は、どんな強みで、どんな市場で、どんなふうに稼ぎ続けられるのか?」
賢い投資とは、数字と物語の両方をそっと手に取ること。
それが、長く市場と付き合うためのいちばんの近道です。






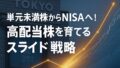
コメント