毎年たくさんの年金法案が改訂され日々 気にしていないといつの間にか法案が改訂され自ら請求しないともらえるものももらえない事態になります。今年度(令和7年度)に国会に提出された年金改革関連の主な3法案で厚労省も重点としている内容の概要をご説明します。
🧾 1.被用者保険の適用拡大(社会保険加入対象の拡大)
- 概要:短時間労働者や中小企業・個人事業主のパートなどにも厚生年金と健康保険をかぶらせる取り組みです。賃金要件の撤廃、2029~35年に企業規模要件の段階的解消、公費負担の軽減措置なども含まれています 。
- 注目点:「106万円の壁」や「130万円の壁」を実質撤廃し、働くママ・パパや非正規雇用者にとって年金加入の壁が下がるようになります。
🧓 2.在職老齢年金制度の見直し
- 概要:年金を受給しながら働く高齢者に対する「年収の壁」(給与と年金の合計が一定額を超えると年金が減る制度)を緩和します。具体的には、支給停止となる合計収入基準を現行の月額50万円から62万円へ引き上げ、750万人規模の高齢者が全額受給可能となる見込みです(令和8年4月施行)。
- メリット:高齢者の労働意欲を損ないにくくし、慢性的な人手不足に一定の対応が期待されます。
👨👩👧👦 3.遺族年金制度の見直し
- 概要:遺族厚生年金において、18歳未満の子がいない20~50代の配偶者への給付を原則5年間に短縮し、60歳未満の男性配偶者も対象にするなど、男女・世代間の不平等是正を進めます。遺族基礎年金(子への給付)も支給対象者基準を見直します(令和10年4月施行)。
- 意図:女性(特に若い配偶者)や多様な家族構成に配慮した、きめ細かな保障制度への転換といえます。
上記の中から「被用者保険の適用拡大(社会保険加入対象の拡大)」について取り上げます。
👩⚕️ 社会保険加入がもっと身近に──2025年以降の被用者保険適用拡大とは?
🔍 はじめに:働き方多様化と社会保障のズレ
2025年5月に国会に提出された令和7年年金制度改正案では、被用者保険の適用拡大が柱の一つです。これまで「扶養の壁」や企業規模で制限されていた社会保険加入が、より多くの働き手にも届くようになります。本記事では、理屈では伝わらない“なぜ今なのか”をわかりやすく解説します。
1. 被用者保険とは?
- 被用者保険=従業員が対象となる厚生年金保険+健康保険の総称
- 正社員以外でも一定の条件を満たせば、短時間労働者にも加入義務が生じます。
✅ メリット:
- 将来受け取る年金額が増える
- 健康保険から傷病手当・出産手当が支給される
- 会社と折半で、自己負担を軽減できる。
2. 適用拡大の背景とスケジュール
🚩 段階的拡大の流れ:
| 年 | 対象企業(厚生年金被保険者) | 内容 |
| 2016年10月 | 501人以上 | 週20h・月額8.8万・1年以上雇用・学生不可など |
| 2022年10月 | 101人以上 | 2ヶ月以上の見込みへ条件緩和 |
| 2024年10月 | 51人以上 | 半数以下の中小企業へ拡大 |
| 2026~2035年 | 36人→21人→11人→全企業へ撤廃予定 |
- 企業規模要件の完全撤廃により、自営業・個人事業主の短時間労働者も対象に。
3. 具体的な加入条件(2024/10以降)
社会保険の加入対象は以下の4つをすべて満たした場合です:
- 週20時間以上
- 月額賃金88,000円以上(年収約106万円以上)
- 雇用見込み2ヶ月以上(2022年以降は「1年以上」から緩和)
- 学生でないこと
これらを満たす短時間労働者は、企業規模にかかわらず加入対象になります。
4. なぜ“今”なのか?社会的背景と目的
📈 少子高齢化・保険料財源の安定化
短時間労働者を社会保険に加えることで、保険料収入を増やし、将来の年金・医療制度の持続可能性を確保します。
⚖️ 働き方の多様化に対応
副業・フリーランスの増加が進む中、所得・就業形態に関係なく保障を一元化し、公平性を高めます。
👩💼 女性・非正規雇用者への支援
106万円の壁撤廃により、子育て中の女性などが、社会保障から除外されるハンディを減らし、就労継続の支援につながります。
5. 制度拡大によるメリット・デメリット
✅ メリット:
- 保障の拡充:傷病・出産時の手当が得られる
- 将来もらえる年金が増える
- 社員との不公平感の解消:パートでも保証が揃う
- 企業向け助成制度あり:「社保適用改善コース」
⚠️ デメリット:
- 手取りが減る可能性:保険料負担が生じる
- 企業の負担増:事業主負担も発生
- 労務管理が複雑化:加入手続きや給与計算に注意が必要
6. 企業・人事が今すべき対応
1 自社の被保険者数を把握:6ヶ月連続で50人以上?。
2 該当労働者を抽出:労働時間・賃金・学生除外…要件を満たす人を確認。
3 従業員への周知:影響範囲とメリット・デメリットを丁寧に説明。
4 手続き準備:社会保険加入・給与システムの連携強化が必須。
5 助成金などの活用:「社保適用促進手当」での補助検討。
7. パート当事者に伝えたいポイント
- 手取り減だけじゃない:今は不都合でも、病気・出産時の保障など将来安心が得られます。
- 106万円の壁撤廃で働きやすく:収入範囲内の働き方に縛られず、キャリア形成が可能に。
- 保険料負担軽減制度も:事業主による支援や社会保障制度の理解を促す企業が増えています。
8. FAQ
Q1:扶養控除はどうなる?
→ 年収が106万円以上になると国保扶養から外れる可能性あり。詳細は税理士に相談を。
Q2:学生でも加入できる?
→ 学生は原則加入対象外ですが、「学生でない」ことが要件のため例外あり。
Q3:副業先でも加入が重なる?
→ 複数雇用でも、雇用保険の被保険者なら合算して加入対象になります。
✍️ まとめ
近年の年金改革において、社会保険の加入対象が短時間労働者にまで広がる流れは、制度の持続性と公平性を兼ね備えた重要な一歩です。企業と個人が適切に理解し、準備を進めることで、安心して働き続けられる社会が実現されます。ご存知のとおり年金法案はみなさんの老後生活に直結する大事な法律です、常に気にとめていただきたい法律の一つです。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3db56b70.538f6602.3db56b71.32d00306/?me_id=1213310&item_id=17899296&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F7277%2F9784478067277.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)



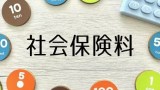



コメント