🔷 はじめに
2025年以降、日本の「遺族年金制度」は大きく変わろうとしています。これまで専業主婦や子どもがいない配偶者への手厚い保障が特徴だった遺族年金制度ですが、少子高齢化や男女平等の観点から制度の見直しが行われ、支給対象・期間・金額に大きな変更が加えられます。
本記事では、遺族年金制度の改正ポイントをわかりやすく整理し、実際に「夫が60歳で死亡した場合」の具体的な受給額シミュレーションを通して、将来の備えについて深く掘り下げます。
✅ 遺族年金制度とは?
日本の遺族年金は主に以下の2種類で構成されています:
- 遺族基礎年金:国民年金(第1号被保険者)が対象。子どもがいる配偶者または子ども本人に支給。
- 遺族厚生年金:厚生年金(第2号被保険者)が対象。配偶者や子に支給。子の有無や配偶者の年齢で支給要件が異なる。
🔶 2025年以降の主な制度改正内容
1. 子のいない配偶者の有期給付化
これまで一部配偶者に終身で支給されていた遺族厚生年金が、原則5年間の有期支給へ移行されます。対象は以下のとおり:
- 20〜50代の子のいない配偶者(男女問わず)
- 結婚期間や被保険者期間により支給額に調整あり
2. 有期給付加算の創設
終身支給から5年に短縮される分、年間の支給額を増加させる加算制度が新設されます。
3. 死亡時分割制度の創設
亡くなった配偶者の老齢厚生年金の一部を、存命配偶者の65歳以降の年金に上乗せする新制度。婚姻期間に応じて分割。
4. 中高齢寡婦加算の廃止
現行制度で40歳以上の妻に支給される**中高齢寡婦加算(月5万円程度)**は段階的に廃止されます。
5. 支給要件の男女平等化
これまで女性に有利だった支給年齢や条件を、男女ともに統一する方向です。
🧮【シミュレーション】夫が60歳で死亡した場合のケース
前提条件:
- 夫:60歳定年退職後、再雇用にて年収380万円。死亡時点で60歳。
- 妻:55歳、会社員で年収300万円。子どもはいない。
- 夫の厚生年金加入期間:40年(報酬比例年金部分のみを想定)
1. 遺族厚生年金の受給可否
- 子どもがいない → 遺族基礎年金は対象外
- 妻は55歳 → 年齢要件クリア(支給対象)
- 改正後 → 5年間の有期支給に移行
2. 支給額の試算(有期支給)
- 夫の年金見込額:年額180万円
- 遺族厚生年金:180万円 × 3/4 = 135万円/年
- 5年間の合計:135万円 × 5年 = 675万円
3. 死亡時分割制度の影響
仮に結婚期間が30年であれば、夫の年金の一部(例:年間20万円程度)を妻が65歳以降の老齢厚生年金に上乗せ可能。生涯ベースで約300〜400万円の増額効果が見込まれます。
4. 中高齢寡婦加算の廃止影響
支給対象だった場合、月5万円相当が廃止 → 年間60万円 × 10年 = 約600万円相当の機会損失
🧭 今後の対策と準備すべきこと(FP視点)
🔹 1. ねんきんネットの活用
公的年金の見込み額を定期的に確認し、ライフプラン表を作成。改正後の制度下でも老後の見通しを可視化。
🔹 2. iDeCo・NISAなど私的年金の充実
支給額が減ることを見越し、老後資金を準備。特に夫婦それぞれでのiDeCo活用が重要です。
🔹 3. 掛け捨て保険の再検討
公的保障の減額を補うため、死亡保障を一時的に充実させる必要も。
🔹 4. 生命保険・医療保険の見直し
保障内容を確認し、「5年だけ必要な生活保障」を民間保険で補完することも選択肢。
🔹 5. 健康経営・副収入の確保
高齢期でも働ける体力と環境づくりが、年金・保険に依存しすぎない生活を支えます。
🌏 今後の法改正の見通し
- 高所得層の厚生年金報酬上限引き上げ
- iDeCoの加入上限年齢の延長(70歳案)
- 障害年金や遺族年金の納付要件緩和
- 在職老齢年金の制度見直し(高齢就業者の年金調整緩和)
📌 まとめ:備えあれば憂いなし
2025年から始まる遺族年金制度の改正は、すべての世帯にとって無関係ではありません。特に子どものいないご夫婦や共働き世帯、定年退職後の家庭では、ライフプランと保障内容の見直しが必須です。
シミュレーションで見たように、675万円という一時的な保障だけでは生活再建には不十分なケースもあります。今こそ、公的年金・私的保障・働き方の三本柱で安心な老後設計を描いていきましょう。
📝 おすすめ記事:
この記事が、読者の皆さまの将来設計の一助になれば幸いです。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/434a3694.cba4c3a0.434a3695.4d158192/?me_id=1285657&item_id=12953692&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbookfan%2Fcabinet%2F01119%2Fbk4528024268.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)






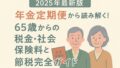
コメント