第1章|まずは「現行の遺族年金」を超カンタンに 🧭
1-1. 二本柱の役割
- 遺族基礎年金(国民年金):「子のある配偶者」or「子」が対象。2025年度の基準額は年831,700円+子の加算(1・2人目 各239,300円、3人目以降 各79,800円)。子は18歳年度末まで(障害1・2級は20歳未満)を目安に支給。
- 遺族厚生年金(厚生年金):亡くなった方の報酬比例部分×3/4が基本。**被保険者期間が300月未満でも「300月みなし」**で計算。
1-2. 65歳以降の“併給調整”の考え方
65歳以上で自身も老齢厚生年金の権利がある場合、
「亡くなった方の報酬比例×3/4」と「亡くなった方の報酬比例×1/2+自分の老齢厚生×1/2」を比較して高い方が遺族厚生年金の額になります(“比較調整”)。
第2章|2025年成立・2028年施行「改正の全体像」🧩
2025年6月13日に年金制度改正法が成立。厚労省の公式ページに遺族厚生年金の見直しが整理されています。施行は原則2028年4月、男女差の解消・働き方の中立性・家族形態の多様化を踏まえた設計です。
2-1. 誰が「5年の有期給付」になるの?
- 男性:子のいない60歳未満の夫も、**施行直後から有期給付(原則5年)**の対象に(新規拡大)。
- 女性:子のいない妻は、2028年度末時点で40歳未満が施行直後から有期給付(原則5年)。その後、20年程度かけて段階的に対象年齢を引き上げ。
2-2. 有期給付でも“手厚く”する仕掛け
- 「有期給付加算」で有期期間中の年金額は“約1.3倍”に増額。5年経過後も、障害状態や低所得(おおむね単身で年122万円程度=地方税所得見直し後は132万円見込み)なら継続給付。概ね月収20~30万円超で継続給付は停止。
- 「収入要件(年収850万円未満)」は撤廃。高収入ゆえの停止という“天井”を外し、働き方を阻害しない方向へ。
2-3. 影響を受けない人(安心リスト)
①既に受給中、②60歳以降に受給権発生、③18歳年度末までの子を養育中、④2028年度に40歳以上の女性は、今回の見直しの影響なし。
2-4. 子育て世帯は“むしろプラス”
**遺族基礎年金の「子の加算」**は、年間約28万円に引き上げ(3人目以降も同額へ統一)。18歳年度末までは現行どおりで、その後さらに5年間は増額された有期給付+継続給付の対象になります。
2-5. 「死亡分割」で将来の老齢厚生年金を底上げ
配偶者死亡時に婚姻期間中の厚生年金記録の一部(法定2分の1ベース)を遺された側へ分ける「死亡分割」を新設。65歳以降の老齢厚生年金額を底上げし、長期の生活保障を強化する狙いです。制度設計は、既存の離婚時分割の考え方を参照。
第3章|「5年で打ち切り」は誤解?よくある質問にその場で回答 🙋♀️🙋♂️
Q1:本当に“5年でゼロ”になるんですか?
A:いいえ。有期期間中は約1.3倍の加算、5年経過後も障害状態/低所得なら継続給付が可能。全面的に“5年で終わり”ではありません。
Q2:いま受給中の人も5年にされる?
A:されません。既受給者や60歳以降の受給権、子を養育中、2028年度に40歳以上の女性は影響なし。
Q3:男性はどう変わる?
A:子のいない60歳未満の夫も原則5年の有期給付対象に。従来の男女差をならす方向です。
Q4:子どもがいる場合は?
A:18歳年度末までは現行どおり。終了後の5年間は増額された有期給付+継続給付の対象に。子の加算額も約28万円/人**へ増額されます。
Q5:65歳以降の“自分の老齢厚生年金”との関係は?
A:比較方式(亡くなった方の報酬比例×3/4 vs 亡くなった方の1/2+自分の1/2)で高い方を適用。これは現行と同様です。
第4章|対象者別「早見」+ライフイベント別の受取りイメージ 🗺️
4-1. 既受給/60歳以降/子育て中/2028年度に40歳以上の女性
→ 影響なし(現行継続)。制度変更に伴う減額や停止の心配は原則不要です。4-2. 子のいない配偶者が60歳未満で死別(施行後)
- 男女共通:原則5年の有期給付
- 有期中は約1.3倍の加算、6年目以降は障害/低所得なら継続
- 年収850万円要件の撤廃で働き方の柔軟性↑。
4-3. 子どもがいる場合(18歳年度末まで)
- 遺族基礎年金+子の加算は現行どおり
- 子の加算は将来“増額”(約28万円/人)
- 18歳年度末以降は5年の増額有期+継続給付の対象に。
第5章|金額の基本式をおさらい(現行)🧮
- 遺族基礎年金:年831,700円+子の加算(1・2人目 各239,300円、3人目以降 各79,800円)。
- 遺族厚生年金:亡くなった方の老齢厚生年金(報酬比例)×3/4。**被保険者期間が300月未満は「300月みなし」**で補正。
🔎 65歳以上の比較計算
A:亡くなった方の報酬比例×3/4
B:亡くなった方の報酬比例×1/2+自分の老齢厚生×1/2
高い方=支給額。
第6章|改正点のメリットとデメリットをフラットに評価 ⚖️
メリット ✅
- 男女差の縮小:男性(60歳未満・子なし)にも有期給付が広がり、家計補強の「橋渡し」機能が明確に。
- 有期中は“約1.3倍”の手厚さ:急な収入減に配慮し、当座の生活費ギャップを埋めやすい。
- 継続給付のセーフティネット:障害/低所得なら6年目以降も支給。就労収入が月20~30万円超まで段階的に調整。
- 子育て世帯の強化:**子の加算引上げ(約28万円/人)**で、教育費・生活費を手当。
- 就労を阻害しない:年収850万円要件の撤廃で、働くほど不利になる“崖”を解消。
- 老後の底上げ:死亡分割で65歳以降の老齢厚生年金額アップが見込める。
デメリット/留意点 ❌
- 「無期」→「有期」化の心理的負担:子のいない60歳未満の配偶者は、有期(原則5年)が前提。**長期プランは“継続給付の条件”や“死亡分割後の老齢厚生”**を踏まえて再設計が必要。
- 中高齢寡婦加算の“新規分”逓減:2028年以降の新規発生分は25年かけて段階的に縮小・終了(既受給者は影響なし)。将来の新規該当者は加算額が従来より小さくなる可能性。
- 制度の段階実施で“わかりにくい”:女性は40歳未満から段階的拡大など、世代によって適用が違う点は注意。
第7章|ケースで理解する(簡易イメージ)🧩
- ケースA:夫(会社員)が死亡、妻38歳・子2人(10歳・8歳)
→ 遺族基礎年金+子の加算が基本。18歳年度末まで現行どおり受給。その後5年間は増額された有期給付+継続給付の対象に(所得・障害要件次第)。子の加算は28万円/人へ引上げ予定。 - ケースB:妻を亡くした夫(55歳・子なし、厚生年金加入中)
→ 施行後は5年の有期給付対象に(男性の新規拡大)。有期中は約1.3倍、6年目以降も条件を満たせば継続。 - ケースC:配偶者死亡時に60歳以上
→ 無期給付(現行どおり)。改正の影響なし。
※厳密な金額試算には加入記録・平均標準報酬・見込老齢年金額などが必要です。制度の骨子は上記のとおりですが、個別の年金額はねんきん定期便/ねんきんネットや年金事務所でご確認を。
第8章|“いま”できる確認リスト ✅
- 自分(または配偶者)の加入記録:被保険者期間・平均標準報酬の把握
- 家族構成と年齢:子の有無/年齢(18歳年度末)・配偶者の年齢が60歳以上か
- 自分の老齢年金見込み:比較調整でどちらが有利かのイメージづくり
- 就労収入の見通し:継続給付の収入弾力(単身で年122万程度→132万見込み。月20~30万円超で停止目安)
- 「死亡分割」適用可否:婚姻期間と厚生年金記録の確認(将来の老齢厚生の底上げ)
第9章|関連する“周辺の見直し”も要チェック 🔄
- 繰下げとの関係(65歳前に遺族権利がある場合):令和7年改正で、令和10年3月31日時点に遺族厚生の権利があり65歳未満の方(昭和38年4月2日以降生まれ)は、老齢厚生は「遺族請求していない」場合に限り繰下げ可/老齢基礎は請求有無にかかわらず繰下げ可へ整理。
第10章|まとめ(編集後記)📝
改正の“見出し”だけを切り取ると「5年で打ち切り」に見えますが、実際は男女差是正と働くことへの中立性を意識しつつ、当座は厚め(約1.3倍)、必要があれば継続、子育て世帯は加算を増額、老後は死亡分割で底上げという全体最適型の設計です。まずは自分の世帯がどのカテゴリに入るかを把握し、個別の年金額と収入見込みを軸に、ライフプランを丁寧に組み直していきましょう。😊




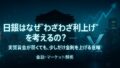

コメント